正月飾りの時期はいつからいつまで?処分の方法は神社or自宅?

お正月の飾りは毎年飾っていますか?
私は飾っている時期や処分の方法がよく分からずに鏡餅くらいしか飾ってなかったりします^^;
そして、鏡餅も何となーく捨てたりしていて、なんだか罰当たりな気が・・・^^;
本当は「正月飾りを華やかに飾ってもてなしてみたい!」と思っています。
そこで、今日は正月飾りの時期はいつからいつまで飾るものなのかと、処分の方法について調べてみました。
神社や自宅どちらで処分するのでしょうか?
正月飾りとは?
正月飾りとは、年神様への目印となる玄関の飾りのことを言います。
年神様とは、元旦に家々へ新年の幸せを運んでくれるために、高い山から降りてきてくれる神様だそうです。(歳徳神、正月様などとも呼ばれています)

昔の人は先祖が田の神や山の神となって、正月に子孫の繁栄を願って幸せを運んできてくれると考えられていました。
そこで、たくさんの幸せを授かりたいがために年神様をお迎えしてお祝いする風習が生まれたということです。新年が良い年でありますようにと願いを込めて飾ります。
正月飾りの種類
正月飾りの種類を紹介します。
飾る物は、地域や宗派等で異りますので、心配な方は親族やご近所の方に聞いてみるのが確実です。
ここでは一般的な正月飾りを紹介します。
■門松(かどまつ)

家の門の前に立てる松や竹の飾りのことです。別名は松飾り(まつかざり)とも言います。
昔は木のこずえに神が宿ると言われていて、門松は年神様を家に迎え入れるための依代(よりしろ)となっています。※依代とは、神や霊がつく対象物のことを言います。
■注連飾り(しめかざり)

神域と現世を分ける結界の意味を持っています。
厄や禍(わざわい)を払ってくれる意味を持っています。
■餅花(もちばな)

エノキや柳の木に小さく餅や団子をさして飾ります。
1年の五穀豊穣を祈願します。
■鏡餅

丸い形は円満を表していて、2つにお餅が重なっているのは重ね重ねを意味しており、円満に年を重ねるということを表しています。
■羽子板

最初は、羽根つきをして遊ぶ道具として使われていましたが、徐々に厄除けの意味とされ、正月にその年に生まれた女の子に無病息災を願うお守りとして購入する習慣がついたと言われています。
■破魔矢(はまや)と破魔弓(はまゆみ)

正月の縁起物として寺院や神社で授与される矢と弓です。
こちらは産まれたばかりの男の子へ厄払いの意味や健やかな成長を願って購入するものとされています。。
正月飾りの時期はいつからいつまで?
「正月飾りを飾る時期はいつからなの?」
という疑問に関してですが、正月事始めと言われる12月13日から12月30日の間が良いとされています。
ただ、現在ではあまりに早く飾るとクリスマス行事と重なって変だと感じる人も多く、一般的には12月26日以降に飾る人が多いようです。
ここで注意!12月29日は「9」がつきますね。
この「9」が「苦」にも通じて縁起が悪いと言われています。
また、12月31日に飾るのを「一夜飾り」と言い、年神様に失礼で礼に欠ける行為と言われています。
正月飾りを飾り付ける時はこの2つの日を避けて飾り付けるといいそうです。
ということで、12月26日、27日、28日、30日のどれかの日に飾り付けるということですね。
そして、
「正月飾りの時期はいつまで?」という疑問に関してですが、
元旦から7日までを松の内と言って、この期間に年神様が家に来てくれると言われており、1月7日まで飾っているのが一般的です。
地域によって異なります。
1月15日の「小正月」までという地域もあれば、1月20日の「二十日正月」までという地域もあります。
正月飾りの処分の方法は神社or自宅?
正月飾りの処分の方法は、一般的には神社に持っていき、「どんど焼き」や「お焚き上げ」で焼いてもらうのが良いそうです。
「どんど焼き」とは、小正月1月15日に行われる行事で、正月の飾りを一か所に積み上げて燃やすと言うものです。

飾りを燃やした後の残り火で、細い竹に刺した団子や餅を食べると、1年間健康でいられるという言い伝えがあるそうで、無病息災・五穀豊穣を願う行事の一つになっています。
「お焚き上げ」とは、火の神の力で天界へ神様を還す意味があり、仏事的には思いが込められたものや、魂が宿る物にこれまでの礼を尽くして浄化によって天に還すのだそうです。

しかし、最近はわざわざ神社に行かなくても…と言う方も多くいて、自宅で処分する方も増えてきているそうです。
自宅で処分するやり方を紹介します。普通のゴミと同じように捨てるのはやはり縁起が良くないようです。
2.その紙の上に飾りを置きます。
3.お清めの塩をお正月飾りに振ります。
4.新聞紙や紙ごとくるんで、新しいごみ袋に入れて、さらに塩を振りかけます。※他の一般ごみと一緒にするのはダメです。
5.感謝の気持ちを込めて、燃えるゴミの日に出します。
自宅の庭で焼く方は、土を神酒(みき)と塩で清めてから、しっかりと焼いてくださいね。

神酒(みき)とは、神様にお供えするお酒のことで、神棚にお供えしたり、神社に奉納したりします。お神酒はお店やネットなどで購入することも可能です。主に日本酒が多くて、白酒、黒酒、清酒、濁酒などです。
以上、今回は正月飾りの時期はいつからいつまでなのか、そして正月飾りの処分の方法(神社と自宅別)について紹介しました。
新年を気持ちよく迎えるために、正月飾りの準備だけではなく、処分方法もしっかりと把握しておかないといけませんね。ただ、捨てていた私は反省だらけでした(^^ゞ
今年は気をつけたいと思います☆彡
ここまで読んで頂いてありがとうございました! もし記事が面白いと感じてもらえましたら、下の「Tweet」などSNSでのシェアしていただけるとすごく嬉しいです☆
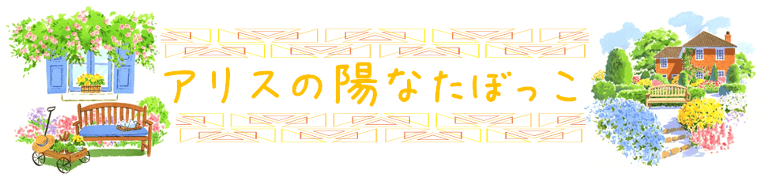



















この記事へのコメントはありません。